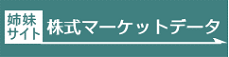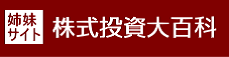|
[�����i���o���ρj]

�ړ����ϐ�
- ���F�F9�J���ړ����ϐ�
- ���F�F24�J���ړ����ϐ�
- �ԐF�F60�J���ړ����ϐ�

 �@�`�F�b�N�|�C���g�I�i4�������_�E�����͌����X�V�j �@�`�F�b�N�|�C���g�I�i4�������_�E�����͌����X�V�j
4�������o�����������́A���������o���{�����W���[�o���h+1�Ђʼn��q�Q�t����W�J�B3���������̂Ńw�b�W�|�C���g���T���E�����Ō��čs�����Ə����Ă��āA���Ȃ肢���|�C���g�ł̃w�b�W�ɂȂ�܂����ˁB���Ȃ����ł��B���o�͏T���E������4���܂ł̃T�|�[�g���C���������Ă܂��̂ŁA����A����܂Ńw�b�W�͂��܂����܂܂ł����Ǝv���܂��B�����ł̓{�����W���[+1�Ђ������Ă��炸�g�����h�͂͌p�����Ă��܂��̂ŁA�����OK���ȂƎv���܂��B
������2018�N����`�����Ă����g���v���g�b�v�̏����2020�N11���ɏ㔲����������㏸�g�����h���������ĕۂ��������`�����A����̓g�����h�̋x�~�̌`�Œʏ�͏㏸�g�����h�p���̌^�Ə����Ă��Ă����Ȃ�܂����ˁB�e�N�j�J���ʂ�̓W�J�ɂȂ�܂����B���o�͒����ł���������Ă܂��̂ŁA�������������̓w�b�W�ł��̂��Ȃ��炵���������Ă����������ȂƎv���܂��B

[�T���i���o���ρj]

�ړ����ϐ�
- ���F�F13�T�ړ����ϐ�
- ���F�F26�T�ړ����ϐ�
- �ԐF�F52�T�ړ����ϐ�

 �@�`�F�b�N�|�C���g�I �@�`�F�b�N�|�C���g�I
�i������5��22�����_�L�ځj
���o�������T���́A3��28���̍��l����Ɠ����̃{�����W���[�o���h+1�Њ��ꂪ�o�����łŃw�b�W�����Ă���A���̂܂�4���܂ł̃T�|�[�g���C����������ăg�����h�]�����Ă��鏊�ł��̂ŁA�l�q���̏��B���̃w�b�W�́A4���܂ł̃T�|�[�g���C�������Ȃ��ԁA���邢�́A�T���̃{�����W���[�o���h+1�Ђ��������^�����ĉ��Ȃ��Ԃ͂������܂ܗl�q���ł����Ǝv���܂��B
�T���̓{�����W���[�o���h���X�N�C�[�Y���Ă��Ă��܂��̂ŕۂ�����������Ă������ȂƎv���܂��B�����ł̓t���b�O�^�ɂ������鏊�ł��ˁB���̕ۂ��������㔲���邩�������邩�Ŏ��̃g�����h�����܂肻���ł��B���o�͉��~�g�����h�����悤�Ȃ�������炩���B�����������o�͔���͂��܂���̂ŁB
���o������������肭�����Ă܂��̂ŁA��������g�����h��点�Ă�����āA���������g�����h�]���̃|�C���g�ł̓w�b�W�����Ă��̂��ł������@�ł����Ǝv���܂��B

[��T�̓����i���o���ρj]

�ړ����ϐ�
- ���F�F5���ړ����ϐ�
- ���F�F10���ړ����ϐ�
- �ԐF�F25���ړ����ϐ�
- �ΐF�F75���ړ����ϐ�
- ���F�F100���ړ����ϐ�
- �I�����W�F�F200���ړ����ϐ�
�{�����W���[�o���h
- �D�F�F�{�����W���[�o���h�i�}1�ЁE�}2�ЁE�}3�Ёj
- ���S���F20��
���S����21����25���ɂ��邱�Ƃ�����܂����A20�����n�}���Ă����Ȃ̂ŁA20����\�������Ă܂��B���Ȃ݂ɁA�{�����W���[�o���h�̊J���҂̃{�����W���[���́A��{�ݒ��20���𐄏����Ă��܂��B
|
�Z���g�����h�̓]���Ƃ�
�Z���g�����h�̓]���̉���́A�ȉ��̃y�[�W���Q�Ƃ��Ă��������B
|

[����̓W�J�\�z�Ɛ헪]
 �@�`�F�b�N�|�C���g�I �@�`�F�b�N�|�C���g�I
�i������5��22�����_�j
���o���ς��������T���̗��ŏ��������ƂƓ��l�ł��B
NY�_�E�i�����j

 �@�`�F�b�N�|�C���g�I �@�`�F�b�N�|�C���g�I
�i������5��21�����_�L�ځj
NY�_�E�́A�o���T�C�g�u�����}�[�P�b�g�f�[�^�v�̌���X�̕��ŏ����܂������A4��3����2�����l���ꂪ�o���̂Ńw�b�W�����A4������̉����̎n�܂��4��4���̑傫�߂̉A���ł��̂ŁA����m�ɗz���Ŕ����Ă��������w�b�W�O���̃|�C���g�Ə����Ă��āA5��10���ɂ��ꂪ�o���̂Ńw�b�W���O���Ă��鏊�ł��B�B
�����A�č����͊������C�ɂȂ鏊�ŁA���l���ɂ����悤�ȏ㏸�ɂȂ����Ƃ��Ă��܂��X�g���Ɖ�����悤�ȑ���ɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA�㏸�ł��Ă����Ă����܂���Ȃ��悤�Ɏv���܂��B����āA���ɒZ���g�����h�̓]�����o�����������̃w�b�W�̃|�C���g�ɂȂ�܂��B
�C�[���h�X�v���b�h��0�ߕӂ܂ŗ��āA�����Δ�Ŋ��͊����ł��̂ŁA�V�K�����Ȃǂ͓��ꂸ�A�ۗL���Ă��锃���|�W�̃w�b�W�|�C���g�������Ă������Ǝv���܂��B����ŁA�V��`���̌^���o��Δ���d�|�����Ǝv���܂��B�V��`���̌^�͑S�R�o�ĂȂ��̂ŁA����������ɂȂ�Ǝv���܂����B
�i�X�_�b�N�i�����j

 �@�`�F�b�N�|�C���g�I �@�`�F�b�N�|�C���g�I
�i������5��21�����_�ŏ����Ă��܂��j
�i�X�_�b�N�́A�����}�[�P�b�g�f�[�^�̌���X�ŏ����܂������A4��2����23�N������̃T�|�[�g���C���ƃ{�����W���[�o���h+1�Њ��ꂪ�o�����Ŕ����|�W�̓w�b�W�A������4��15���Ƀ{�����W���[�o���h-1�Њ��ꂪ�o���̂ŐV�K���肵�A4��26���̃{�����W���[�o���h-1�Д����Ŕ���|�W�̓w�b�W�B�����āA�i�X�_�b�N��3���̍��l�������������Ńw�b�W����������|�W�͑S���ςŗ��m�B�Ɠ����ɔ����|�W�̃w�b�W���O���A�g�����h�ɍڂ��Ă��鏊�ł��B����|�W�͂قƂ�ǎ��Ȃ������ł��ˁB�\����Ȃ������ł��B����A�{�����W���[�o���h���L��������Ԃ���̃g�����h�ł��̂ŁA�㏸�g�����h���債���g�����h�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B�����|�W�̎��̃w�b�W�|�C���g�́A�Z���g�����h�̓]�����o�����A���邢�́A3�����l���炻������Ă܂���̂ŁA3�����l���ꂪ�o�������ȂƎv���܂��B
�h���~

 �@�`�F�b�N�|�C���g�I �@�`�F�b�N�|�C���g�I
�i������5��21�����_�ŏ����Ă��܂��j
�h���~��4������5�����̈ב։�����X�p�C�N�n�C�̌`�����ĝ���ł��鏊�ł��B�ʏ�X�p�C�N�n�C�̓g�����h�]���ňȌ㉺�����₷���^�ł����A�l�H�ł��̂łǂ����ȂƂ������ł��B�|�C���g��2�ŁA�X�p�C�N�n�C�ł�����4��29�����l����������X�p�C�N�n�C�̔ے�ɂȂ�A5��3���̈��l���ꂪ�o��Ή��~�g�����h�A�Ƃ������ł��B������Ƌ�������܂����A���̊Ԃł����傲�������Ă���Ԃ̓|�W�V�����X����ȂƂ��Ȃ����������Ǝv���܂��B
���āA�d�v���h���C���f�b�N�X�ł����A

�h���C���f�b�N�X�̐��ڂ́u�h���C���f�b�N�X�i�h���w���j �v�Ŋm�F�ł��܂��B
�h���C���f�b�N�X��5��15���Ƀt���b�O�^�̃T�|�[�g�X���C�������������Ŕ����̓w�b�W�̈���A�V�K����A�ēx�t���b�O�^�̃T�|�[�g���C�����㔲����Δ����|�W�̓w�b�W�O���ŁA�V�K����͑���ɂȂ�܂��B
��������ɂ�������ɂȂ��Ă��Ă܂��ˁB�܂��A���̃t���b�O�^�͂���1�����ȏ�o���Ă���A�㔲���悤���������悤���M���x���������Ă���^�ɂȂ��Ă��Ă��܂��̂ł�����Ƃ��ɂ����ł��ˁB
�h���͐헪�łقڑS���̔g��肱�Ȃ��āA����ȏ�Ȃ����炢�\�����Ă��܂������A�����ł����ƕۂ������̒��S���炢�̈ʒu�Ńg�����h�Ȃ��ł����A�Ƃ�ɂ������ꑱ���悤�Ȃ��U�S���ςŗ��m���āA�����d�|�����̌^���o��܂Ńh���C���f�b�N�X���x�݂��Ă��������ȂƎv���Ă��܂��B�܂��ł�����������Ƃ��܂��傤���B
���T�͂����܂łł����A���������Y�ꂽ���Ƃ⑊�ꌩ�čl�����ς�����ꍇ�́u�����}�[�P�b�g�f�[�^�v�̃c�C�b�^�[�ŏ����܂��B
|
���́u���߂̃e�N�j�J�����́v�̗��́A�T���X�V���Ă��܂��B���X�̓��o���ςȂǂ̑���ɉ������e�N�j�J�����͂́A�o���T�C�g�u�����헪�v��charTrade�ɏ����Ă��܂��BcharTrade�̓e�N�j�J�����͂�y��Ƃ��Ă���A�e�N�j�J�����͂̉���́A�o���T�C�g�u����������S���v�́u�e�N�j�J�������v�̃y�[�W�ō��ڂ��Ƃɉ�����Ă��܂��̂ŁA��������Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B
|
�e�N�j�J�����͂�charTrade�̊�b�҂��Q�l��
���ʖ@�[�r���~�b�f�B���O�[
|
 �@�����Əڂ���
�@�����Əڂ��� �@�����Əڂ���
�@�����Əڂ���